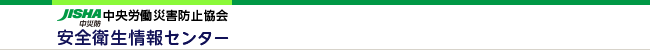
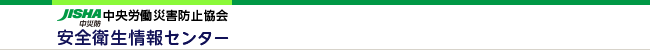
|
別 紙(平成18年3月31日基発第0331023号により廃止) 安全管理者能力向上教育(初任時)カリキュラム
科目 |
範囲 |
細目 |
時間 |
| 1 安全管理者の役割等 | (1) 労働災害の現状と問題点 | イ 労働災害の現状 | 1.0 |
| ロ その問題点 | |||
| (2) 企業経営と安全 | イ 安全と生産 | ||
| ロ 安全と経営損失の防止 | |||
| ハ 経営者の安全責務 | |||
| (3) 安全管理者の役割と職務 | イ 安全管理体制 | ||
| ロ 安全管理者の役割 | |||
| ハ 安全管理者の職務 | |||
| 2 安全管理の進め方 | (1) 災害原因分析の方法とその活用 | イ 災害発生のメカニズム | 2.0 |
| ロ 不安全な状態と不安全な行動 | |||
| ハ 災害調査 | |||
| ニ 災害原因の分析 | |||
| ホ 災害原因分析の活用 | |||
| (2) 危険性の事前評価の方法 | イ 危険性の種類 | ||
| ロ 工場の新設・増設時の事前評価 | |||
| ハ 化学物質の危険性の事前評価 | |||
| ニ 化学プラントの事前評価 | |||
| (3) 安全管理計画の立て方 | イ トップの安全管理方針の明示 | ||
| ロ 安全管理計画の内容 | |||
| ハ 安全管理計画作成の留意点 | |||
| ニ 安全管理計画作成のプロセス | |||
| (4) 中高年齢労働者等への配慮事項 | イ 中高年齢労働者の安全対策 | ||
| ロ 身体障害者への安全配慮 | |||
| ハ パートタイム労働者等への安全配慮 | |||
| (5) 総合安全管理の進め方 | イ 総合安全管理体制 | ||
| ロ 災害防止のための連絡協議組織の設置と運営 | |||
| ハ 下請事業場の労働者に使用させる建設物、設備の維持管理 | |||
| ニ 下請事業場が行う安全教育についての指導及び援助 | |||
| 3 機械設備・環境の安全化 | (1) 機械設備・環境の安全化の進め方 | イ 機械設備のレイアウト | 2.0 |
| ロ 機械設備の安全条件 | |||
| ハ 本質安全化 | |||
| ニ 機械設備の設置前の安全審査 | |||
| ホ 機械設備の安全対策 | |||
| ヘ 環境の安全化と整備 | |||
| (2) 安全点検 | イ 安全点検制度の検討 | ||
| ロ 安全点検の結果に基づく欠陥の是正 | |||
| ハ 安全点検の方法 | |||
| 4 教育及び指導の方法 | (1) 教育計画の立て方 | イ 教育計画の必要性 | 2.0 |
| ロ 安全衛生業務従事者に対する能力向上教育 | |||
| ハ 新規採用者、危険業務従事者、新任職長等の安全教育 | |||
| ニ 現に危険業務に従事する者に対する定期教育等 | |||
| (2) 教育の方法 | イ 実施方法 | ||
| ロ 実施に当たっての留意事項 | |||
| ハ 教育効果の評価と持続 | |||
| (3) 作業標準の作成と周知 | イ 作業分析と作業標準 | ||
| ロ 作業標準への正しい理解 | |||
| ハ 作業標準の要件 | |||
| ニ 作業標準の作成 ホ 作業標準の周知徹底 |
|||
| (4) 安全意識の高揚の方法 | イ 主要な方法及び留意事項 | ||
| 5 災害事例及び関係法令 | (1) 災害事例とその防止対策 | イ 災害事例の提示 | 2.0 |
| ロ 災害発生の原因及び防止対策の検討 | |||
| (2) 労働安全衛生法令 | イ 労働安全衛生法 | ||
| ロ 労働安全衛生法施行令 | |||
| ハ 労働安全衛生規則及び関係規則 | |||
計 |
9.0 |
注:「3 機械設備・環境の安全化」の時間数は、設備等の設置状況により2〜4時間の範囲で
適切な時間数を設定すること。