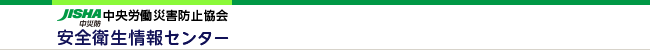安全衛生情報センター
働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律による改正後の労働基準法関係の解釈について
働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律による改正後の労働基準法関係の解釈について
働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成30年法律第71号。以下「整備法」とい う。)による改正後の労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「法」という。)、働き方改革を推進するた めの関係法律の整備に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(平成30年厚生 労働省令第112号)による改正後の労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号。以下「則」という。)及 び労働基準法第三十六条第一項の協定で定める労働時間の延長及び休日の労働について留意すべき事項等 に関する指針(平成30年厚生労働省告示第323号。以下「指針」という。)の内容等については、平成30年 9月7日付け基発0907第1号「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律による改正後の労 働基準法の施行について」により通知したところであるが、これらの解釈については下記によることとす るので、了知の上、取扱いに遺漏なきを期されたい。
第1 フレックスタイム制(法第32条の3関係)
| <時間外・休日労働協定及び割増賃金との関係> | |
| 問1 | 清算期間が1箇月を超える場合において、清算期間を1箇月ごとに区分した各期間を平均して1週間当たり50時間を超えて労働させた場合、法第36条第1項の協定(以下「時間外・休日労働協定」という。)の締結と割増賃金の支払は必要か。 |
| 答1 | 清算期間が1箇月を超える場合において、清算期間を1箇月ごとに区分した各期間を平均して1週間当たり50時間を超えて労働させた場合は時間外労働に該当するものであり、時間外・休日労働協定の締結及び届出を要し、清算期間の途中であっても、当該各期間に対応した賃金支払日に割増賃金を支払わなければならない。 |
| <時間外・休日労働協定における協定事項> | |
| 問2 | フレックスタイム制において時間外・休日労働協定を締結する際、現行の取扱いでは1日について延長することができる時間を協定する必要はなく、清算期間を通算して時間外労働をすることができる時間を協定すれば足りるとしているが、今回の法改正後における取扱い如何。 |
| 答2 | 1日について延長することができる時間を協定する必要はなく、1箇月及び1年について協定すれば足りる。 |
| <月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率の適用> | |
| 問3 | 法第37条第1項ただし書により、月60時間を超える時間外労働に対しては5割以上の率で計算した割増賃金を支払う必要があるが、清算期間が1箇月を超えるフレックスタイム制に対してはどのように適用するのか。 |
| 答3 | 清算期間を1箇月ごとに区分した各期間を平均して1週間当たり50時間を超えて労働させた時間については、清算期間の途中であっても、時間外労働としてその都度割増賃金を支払わなければならず、当該時間が月60時間を超える場合は法第37条第1項ただし書により5割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。 また、清算期間を1箇月ごとに区分した各期間の最終の期間においては、当該最終の期間を平均して1週間当たり50時間を超えて労働させた時間に加えて、当該清算期間における総実労働時間から、①当該清算期間の法定労働時間の総枠及び②当該清算期間中のその他の期間において時間外労働として取り扱った時間を控除した時間が時間外労働時間として算定されるものであり、この時間が60時間を超える場合には法第37条第1項ただし書により5割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。 |
| <法第36条第6項第2号及び第3号の適用> | |
| 問4 | 法第36条第6項第2号及び第3号は、清算期間が1箇月を超えるフレックスタイム制に対してはどのように適用するのか。 |
| 答4 | 清算期間が1箇月を超える場合のフレックスタイム制においては、法第36条第6項第2号及び第3号は、清算期間を1箇月ごとに区分した各期間について、当該各期間(最終の期間を除く。)を平均して1週間当たり50時間を超えて労働させた時間に対して適用される。 また、清算期間を1箇月ごとに区分した各期間の最終の期間においては、当該最終の期間を平均して1週間当たり50時間を超えて労働させた時間に加えて、当該清算期間における総実労働時間から、①当該清算期間の法定労働時間の総枠及び②当該清算期間中のその他の期間において時間外労働として取り扱った時間を控除した時間が時間外労働時間として算定されるものであり、この時間について法第36条第6項第2号及び第3号が適用される。 なお、フレックスタイム制は、労働者があらかじめ定められた総労働時間の範囲内で始業及び終業の時刻を選択し、仕事と生活の調和を図りながら働くための制度であり、長時間の時間外労働を行わせることは、フレックスタイム制の趣旨に合致しないことに留意すること。 |
第2 時間外労働の上限規制(法第36条及び第139条から第142条まで関係)
| <時間外・休日労働協定の対象期間と有効期間> | |
| 問1 | 時間外・休日労働協定の対象期間と有効期間の違い如何。 |
| 答1 | 時間外・休日労働協定における対象期間とは、法第36条の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる期間をいい、1年間に限るものであり、時間外・休日労働協定においてその起算日を定めることによって期間が特定される。 これに対して、時間外・休日労働協定の有効期間とは、当該協定が効力を有する期間をいうものであり、対象期間が1年間に限られることから、有効期間は最も短い場合でも原則として1年間となる。また、時間外・休日労働協定について定期的に見直しを行う必要があると考えられることから、有効期間は1年間とすることが望ましい。 なお、時間外・休日労働協定において1年間を超える有効期間を定めた場合の対象期間は、当該有効期間の範囲内において、当該時間外・休日労働協定で定める対象期間の起算日から1年ごとに区分した各期間となる。 |
| <1日、1箇月及び1年以外の期間についての協定> | |
| 問2 | 時間外・休日労働協定において、1日、1箇月及び1年以外の期間について延長時間を定めることはできるか。定めることができる場合、当該延長時間を超えて労働させた場合は法違反となるか。 |
| 答2 | 1日、1箇月及び1年に加えて、これ以外の期間について延長時間を定めることも可能である。この場合において、当該期間に係る延長時間を超えて労働させた場合は、法第32条違反となる。 |
| <1年単位の変形労働時間制の対象期間の一部が含まれる場合> | |
| 問3 | 対象期間とする1年間の中に、対象期間が3箇月を超える1年単位の変形労働時間制の対象期間の一部が含まれている場合の限度時間は、月42時間かつ年320時間か。 |
| 答3 | 時間外・休日労働協定で対象期間として定められた1年間の中に、対象期間が3箇月を超える1年単位の変形労働時間制の対象期間が3箇月を超えて含まれている場合には、限度時間は月42時間及び年320時間となる。 |
| <限度時間等を超える協定の効力> | |
| 問4 | 法第36条第4項に規定する限度時間又は同条第5項に規定する1箇月及び1年についての延長時間の上限(1箇月について休日労働を含んで100時間未満、1年について720時間)若しくは月数の上限(6箇月)を超えている時間外・休日労働協定の効力如何。 |
| 答4 | 設問の事項は、いずれも法律において定められた要件であり、これらの要件を満たしていない時間外・休日労働協定は全体として無効である。 |
| <対象期間の途中における破棄・再締結> | |
| 問5 | 対象期間の途中で時間外・休日労働協定を破棄・再締結し、対象期間の起算日を当初の時間外・休日労働協定から変更することはできるか。 |
| 答5 | 時間外労働の上限規制の実効性を確保する観点から、法第36条第4項の1年についての限度時間及び同条第5項の月数は厳格に適用すべきものであり、設問のように対象期間の起算日を変更することは原則として認められない。 なお、複数の事業場を有する企業において、対象期間を全社的に統一する場合のように、やむを得ず対象期間の起算日を変更する場合は、時間外・休日労働協定を再締結した後の期間においても、再締結後の時間外・休日労働協定を遵守することに加えて、当初の時間外・休日労働協定の対象期間における1年の延長時間及び限度時間を超えて労働させることができる月数を引き続き遵守しなければならない。 |
| <限度時間を超えて労働させる必要がある場合> | |
| 問6 | 法第36条第5項に規定する「通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に第三項の限度時間を超えて労働させる必要がある場合」とは具体的にどのような状態をいうのか。 |
| 答6 | 「通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に第三項の限度時間を超えて労働させる必要がある場合」とは、全体として1年の半分を超えない一定の限られた時期において一時的・突発的に業務量が増える状況等により限度時間を超えて労働させる必要がある場合をいうものであり、「通常予見することのできない業務量の増加」とは、こうした状況の一つの例として規定されたものである。 その上で、具体的にどのような場合を協定するかについては、労使当事者が事業又は業務の態様等に即して自主的に協議し、可能な限り具体的に定める必要があること。 なお、法第33条の非常災害時等の時間外労働に該当する場合はこれに含まれないこと。 |
| <転勤の場合> | |
| 問7 | 同一企業内のA事業場からB事業場へ転勤した労働者について、①法第36条第4項に規定する限度時間、②同条第5項に規定する1年についての延長時間の上限、③同条第6項第2号及び第3号の時間数の上限は、両事業場における当該労働者の時間外労働時間数を通算して適用するのか。 |
| 答7 | ①法第36条第4項に規定する限度時間及び②同条第5項に規定する1年についての延長時間の上限は、事業場における時間外・休日労働協定の内容を規制するものであり、特定の労働者が転勤した場合は通算されない。 これに対して、③同条第6項第2号及び第3号の時間数の上限は、労働者個人の実労働時間を規制するものであり、特定の労働者が転勤した場合は法第38条第1項の規定により通算して適用される。 |
| <法第36条第6項第3号の適用範囲> | |
| 問8 | 法第36条第6項第3号に規定する要件は、改正法施行前の期間や経過措置の期間も含めて満たす必要があるのか。 また、複数の時間外・休日労働協定の対象期間をまたぐ場合にも適用されるものであるか。 |
| 答8 | 法第36条第6項第3号の要件については、同号の適用がない期間(整備法の施行前の期間、整備法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされている期間及び法第139条から第142条までの規定により法第36条第6項の規定が適用されない期間)の労働時間は算定対象とならない。 また、法第36条第6項第3号の規定は、複数の時間外・休日労働協定の対象期間をまたぐ場合にも適用されるものである。 |
| <指針に適合しない時間外・休日労働協定の効力> | |
| 問9 | 指針に適合しない時間外・休日労働協定の効力如何。 |
| 答9 | 指針は、時間外・休日労働を適正なものとするために留意すべき事項等を定めたものであり、法定要件を満たしているが、指針に適合しない時間外・休日労働協定は直ちには無効とはならない。 なお、指針に適合しない時間外・休日労働協定は、法第36条第9項の規定に基づく助言及び指導の対象となるものである。 |
| <適用猶予・除外業務等に係る届出様式の取扱い> | |
| 問10 | 適用猶予・除外業務等について上限規制の枠内の時間外・休日労働協定を届け出る場合に、則様式第9号又は第9号の2を使用することは差し支えないか。 |
| 答10 | 法第36条の適用が猶予・除外される対象であっても、同条に適合した時間外・休日労働協定を締結することが望ましい。 |
| <中小事業主に係る届出様式の取扱い> | |
| 問11 | 改正前の労働基準法施行規則様式第9号(以下「旧様式」という。)により届け出るべき時間外・休日労働協定を則様式第9号(以下「新様式」という。)により届け出ることは可能か。 また、その際、チェックボックスへのチェックを要するか。 |
| 答11 | 新様式の記載項目は、旧様式における記載項目を包含しており、旧様式により届け出るべき時間外・休日労働協定を新様式により届け出ることは差し支えない。 旧様式により届け出るべき時間外・休日労働協定が新様式で届け出られた際は、改正前の法及び則並びに労働基準法第三十六条第一項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準(平成10年労働省告示第154号)に適合していれば足り、法第36条第6項第2号及び第3号に定める要件を満たすことについて協定しない場合には、チェックボックスへのチェックは要しない。 |
| <指針第8条第2号の深夜業の回数制限> | |
| 問12 | 指針第8条第2号に規定する健康確保措置の対象には、所定労働時間内の深夜業の回数も含まれるのか。 また、目安となる回数はあるか。 |
| 答12 | 指針第8条第2号に規定する健康確保措置の対象には、所定労働時間内の深夜業の回数制限も含まれるものである。なお、交替制勤務など所定労働時間に深夜業を含んでいる場合には、事業場の実情に合わせ、その他の健康確保措置を講ずることが考えられる。 また、指針は、限度時間を超えて労働させる労働者に対する健康及び福祉を確保するための措置として望ましい内容を規定しているものであり、深夜業を制限する回数の設定を含め、その具体的な取扱いについては、労働者の健康及び福祉を確保するため、各事業場の業務の実態等を踏まえて、必要な内容を労使間で協定すべきものである。例えば、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第66条の2の規定に基づく自発的健康診断の要件として、1月当たり4回以上深夜業に従事したこととされていることを参考として協定することも考えられる。 |
| <指針第8条第3号の休息時間> | |
| 問13 | 指針第8条第3号の「休息時間」とはどのような時間か。目安となる時間数はあるか。 |
| 答13 | 指針第8条第3号の「休息時間」は、使用者の拘束を受けない時間をいうものであるが、限度時間を超えて労働させる労働者に対する健康及び福祉を確保するための措置として望ましい内容を規定しているものであり、休息時間の時間数を含め、その具体的な取扱いについては、労働者の健康及び福祉を確保するため、各事業場の業務の実態等を踏まえて、必要な内容を労使間で協定すべきものである。 |
| <法第36条第11項に規定する業務の範囲> | |
| 問14 | 法第36条第11項に規定する「新たな技術、商品又は役務の研究開発に係る業務」の具体的な範囲如何。 |
| 答14 | 法第36条第11項に規定する「新たな技術、商品又は役務の研究開発に係る業務」は、専門的、科学的な知識、技術を有する者が従事する新技術、新商品等の研究開発の業務をいい、既存の商品やサービスにとどまるものや、商品を専ら製造する業務などはここに含まれないこと。 |
| <則第69条第1項第3号の対象となる範囲> | |
| 問15 | 則第69条第1項第3号の対象となる範囲如何。 |
| 答15 | 建設現場における交通誘導警備の業務を主たる業務とする労働者を指すものである。 |
| <自動車の運転の業務の範囲> | |
| 問16 | |
| 答16 | 法第140条及び則第69条第2項に規定する「自動車の運転の業務」に従事する者は、自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(平成元年労働省告示第7号。以下「改善基準告示」という。)第1条の自動車運転者と範囲を同じくするものである。 すなわち、改善基準告示第1条の「自動車の運転に主として従事する者」が対象となるものであり、物品又は人を運搬するために自動車を運転することが労働契約上の主として従事する業務となっている者は原則として該当する。(ただし、物品又は人を運搬するために自動車を運転することが労働契約上の主として従事する業務となっていない者についても、実態として物品又は人を運搬するために自動車を運転する時間が現に労働時間の半分を超えており、かつ、当該業務に従事する時間が年間総労働時間の半分を超えることが見込まれる場合には、「自動車の運転に主として従事する者」として取り扱うこと。) そのため、自動車の運転が労働契約上の主として従事する業務でない者、例えば、事業場外において物品等の販売や役務の提供、取引契約の締結・勧誘等を行うための手段として自動車を運転する者は原則として該当しない。 なお、労働契約上、主として自動車の運転に従事することとなっている者であっても、実態として、主として自動車の運転に従事することがなければ該当しないものである。 |
| <「医業に従事する医師」の範囲> | |
| 問17 | 法第141条に規定する「医業に従事する医師」の範囲如何。 |
| 答17 | 労働者として使用され、医行為を行う医師をいう。なお、医行為とは、当該行為を行うに当たり、医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある行為をいうものである。 |
| <労働者派遣事業の場合> | |
| 問18 | 労働者派遣事業を営む事業主が、法第139条から第142条までに規定する事業又は業務に労働者を派遣する場合、これらの規定は適用されるのか。 また、事業場の規模により法第36条の適用が開始される日が異なるが、派遣元又は派遣先のいずれの事業場の規模について判断すればよいか。 |
| 答18 | 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。以下「労働者派遣法」という。)第44条第2項前段の規定により、派遣中の労働者の派遣就業に係る法第36条の規定は派遣先の使用者について適用され、同項後段の規定により、時間外・休日労働協定の締結・届出は派遣元の使用者が行うこととなる。 このため、法第139条から第142条までの規定は派遣先の事業又は業務について適用されることとなり、派遣元の使用者においては、派遣先における事業・業務の内容を踏まえて時間外・休日労働協定を締結する必要がある。 また、事業場の規模についても、労働者派遣法第44条第2項前段の規定により、派遣先の事業場の規模によって判断することとなる。 時間外・休日労働協定の届出様式については、派遣先の企業規模や事業内容、業務内容に応じて適切なものを使用することとなる。 |
| <一般則適用業務と適用除外・猶予業務等との間で転換した場合> | |
| 問19 | 法第36条の規定が全面的に適用される業務(以下「一般則適用業務」という。)と法第36条の適用除外・猶予業務等との間で業務転換した場合や出向した場合の取扱い如何。 |
| 答19 | 【業務転換の場合】 同一の時間外・休日労働協定によって時間外労働を行わせる場合は、対象期間の途中で業務を転換した場合においても、対象期間の起算日からの当該労働者の時間外労働の総計を当該時間外・休日労働協定で定める延長時間の範囲内としなければならない。したがって、例えば法第36条の適用除外・猶予業務から一般則適用業務に転換した場合、当該協定における一般則適用業務の延長時間(最大1年720時間)から、適用除外・猶予業務において行った時間外労働時間数を差し引いた時間数まで時間外労働を行わせることができ、適用除外・猶予業務において既に年720時間を超える時間外労働を行っていた場合は、一般則適用業務への転換後に時間外労働を行わせることはできない。 なお、法第36条第6項第2号及び第3号の規定は、時間外・休日労働協定の内容にかかわらず、一般則適用業務に従事する期間における実労働時間についてのみ適用されるものである。 【出向の場合】 出向先において出向元とは別の時間外・休日労働協定の適用を受けることとなる場合は、出向元と出向先との間において特段の取決めがない限り、出向元における時間外労働の実績にかかわらず、出向先の時間外・休日労働協定で定める範囲内で時間外・休日労働を行わせることができる。 ただし、一般則適用業務の実労働時間については、法第36条第6項第2号及び第3号の要件を満たす必要があり、法第38条第1項により出向の前後で通算される。 |
第3 年5日以上の年次有給休暇の確実な取得(法第39条第7項及び第8項関係)
| <使用者による時季指定> | |
| 問1 | 法第39条第7項に規定する使用者による時季指定は、いつ行うのか。 |
| 答1 | 法第39条第7項に規定する使用者による時季指定は、必ずしも基準日からの1年間の期首に限られず、当該期間の途中に行うことも可能である。 |
| <使用者による時季指定の対象となる労働者> | |
| 問2 | 法第39条第7項に規定する「有給休暇の日数が十労働日以上である労働者」には、同条第3項の比例付与の対象となる労働者であって、前年度繰越分の有給休暇と当年度付与分の有給休暇とを合算して初めて10労働日以上となる者も含まれるのか。 |
| 答2 | 法第39条第7項の「有給休暇の日数が十労働日以上である労働者」は、基準日に付与される年次有給休暇の日数が10労働日以上である労働者を規定したものであり、同条第3項の比例付与の対象となる労働者であって、今年度の基準日に付与される年次有給休暇の日数が10労働日未満であるものについては、仮に、前年度繰越分の年次有給休暇も合算すれば10労働日以上となったとしても、「有給休暇の日数が十労働日以上である労働者」には含まれない。 |
| <半日単位・時間単位による時季指定の可否> | |
| 問3 | 法第39条第7項の規定による時季指定を半日単位や時間単位で行うことはできるか。 |
| 答3 | 則第24条の6第1項の規定により労働者の意見を聴いた際に半日単位の年次有給休暇の取得の希望があった場合においては、使用者が法第39条第7項の年次有給休暇の時季指定を半日単位で行うことは差し支えない。この場合において、半日の年次有給休暇の日数は0.5日として取り扱うこと。 また、法第39条第7項の規定による時季指定を時間単位年休で行うことは認められない。 |
| <前年度から繰り越された年次有給休暇の取扱い> | |
| 問4 | 前年度からの繰越分の年次有給休暇を取得した場合は、その日数分を法第39条第7項の規定により使用者が時季指定すべき5日の年次有給休暇から控除することができるか。 |
| 答4 | 前年度からの繰越分の年次有給休暇を取得した場合は、その日数分を法第39条第7項の規定により使用者が時季指定すべき5日の年次有給休暇から控除することとなる。 なお、法第39条第7項及び第8項は、労働者が実際に取得した年次有給休暇が、前年度からの繰越分の年次有給休暇であるか当年度の基準日に付与された年次有給休暇であるかについては問わないものである。 |
| <事後における時季変更の可否> | |
| 問5 | 労働基準法第39条第7項の規定により指定した時季を、使用者又は労働者が事後に変更することはできるか。 |
| 答5 | 法第39条第7項の規定により指定した時季について、使用者が則第24条の6に基づく意見聴取の手続を再度行い、その意見を尊重することによって変更することは可能である。 また、使用者が指定した時季について、労働者が変更することはできないが、使用者が指定した後に労働者に変更の希望があれば、使用者は再度意見を聴取し、その意見を尊重することが望ましい。 |
| <義務の履行が不可能な場合> | |
| 問6 | 基準日から1年間の期間(以下「付与期間」という。)の途中に育児休業が終了した労働者等についても、5日の年次有給休暇を確実に取得させなければならないか。 |
| 答6 | 付与期間の途中に育児休業から復帰した労働者等についても、法第39条第7項の規定により5日間の年次有給休暇を取得させなければならない。 ただし、残りの期間における労働日が、使用者が時季指定すべき年次有給休暇の残日数より少なく、5日の年次有給休暇を取得させることが不可能な場合には、その限りではない。 |
| <年5日を超える時季指定の可否> | |
| 問7 | 使用者は、5日を超える日数について法第39条第7項による時季指定を行うことができるか。 |
| 答7 | 労働者の個人的事由による取得のために労働者の指定した時季に与えられるものとして一定の日数を留保する観点から、法第39条第7項の規定による時季指定として5日を超える日数を指定することはできない。 また、使用者が時季指定を行うよりも前に、労働者自ら請求し、又は計画的付与により具体的な年次有給休暇日が特定されている場合には、当該特定されている日数について使用者が時季指定することはできない(法第39条第8項)。 |
| <時季指定後に労働者が自ら年次有給休暇を取得した場合> | |
| 問8 | 法第39条第7項の規定によりあらかじめ使用者が時季指定した年次有給休暇日が到来するより前に、労働者が自ら年次有給休暇を取得した場合は、当初使用者が時季指定した日に労働者が年次有給休暇を取得しなくても、法第39条第7項違反とはならないか。 |
| 答8 | 設問の場合は労働者が自ら年次有給休暇を5日取得しており、法第39条第7項違反とはならない。なお、この場合において、当初使用者が行った時季指定は、使用者と労働者との間において特段の取決めがない限り、当然に無効とはならない。 |
| <端数の取扱い> | |
| 問9 | 則第24条の5第2項においては、基準日又は第一基準日を始期として、第二基準日から1年を経過する日を終期とする期間の月数を12で除した数に5を乗じた日数について時季指定する旨が規定されているが、この「月数」に端数が生じた場合の取扱い如何。また、同規定により算定した日数に1日未満の端数が生じた場合の取扱い如何。 |
| 答9 | 則第24条の5第2項を適用するに当たっての端数については原則として下記のとおり取り扱うこととするが、この方法によらず、月数について1箇月未満の端数をすべて1箇月に切り上げ、かつ、使用者が時季指定すべき日数について1日未満の端数をすべて1日に切り上げることでも差し支えない。 【端数処理の方法】
(例)第一基準日が10月22日、第二基準日が翌年4月1日の場合
|
| <意見聴取の具体的な内容> | |
| 問10 | 則第24条の6の意見聴取やその尊重の具体的な内容如何。 |
| 答10 | 則第24条の6第1項の意見聴取の内容としては、法第39条第7項の基準日から1年を経過する日までの間の適時に、労働者から年次有給休暇の取得を希望する時季を申告させることが考えられる。 また、則第24条の6第2項の尊重の内容としては、できる限り労働者の希望に沿った時季を指定するよう努めることが求められるものである。 |
| <労働者自ら取得した半日年休・時間単位年休の取扱い> | |
| 問11 | 労働者自らが半日単位又は時間単位で取得した年次有給休暇の日数分については、法第39条第8項が適用されるか。 |
| 答11 | 労働者が半日単位で年次有給休暇を取得した日数分については、0.5日として法第39条第8項の「日数」に含まれ、当該日数分について使用者は時季指定を要しない。なお、労働者が時間単位で年次有給休暇を取得した日数分については、法第39条第8項の「日数」には含まれない。 |
| <事業場が独自に設けている特別休暇の取扱い> | |
| 問12 | 事業場が独自に設けている法定の年次有給休暇と異なる特別休暇を労働者が取得した日数分については、法第39条第8項が適用されるか。 |
| 答12 | 法定の年次有給休暇とは別に設けられた特別休暇(たとえば、法第115条の時効が経過した後においても、取得の事由及び時季を限定せず、法定の年次有給休暇を引き続き取得可能としている場合のように、法定の年次有給休暇日数を上乗せするものとして付与されるものを除く。以下同じ。)を取得した日数分については、法第39条第8項の「日数」には含まれない。 なお、法定の年次有給休暇とは別に設けられた特別休暇について、今回の改正を契機に廃止し、年次有給休暇に振り替えることは法改正の趣旨に沿わないものであるとともに、労働者と合意をすることなく就業規則を変更することにより特別休暇を年次有給休暇に振り替えた後の要件・効果が労働者にとって不利益と認められる場合は、就業規則の不利益変更法理に照らして合理的なものである必要がある。 |
| <年次有給休暇管理簿の作成> | |
| 問13 | 年次有給休暇管理簿に記載すべき「日数」とは何を記載すべきか。 また、電子機器を用いて磁気ディスク、磁気テープ、光ディスク等により年次有給休暇管理簿を調整することはできるか。 |
| 答13 | 年次有給休暇管理簿に記載すべき「日数」としては、労働者が自ら請求し取得したもの、使用者が時季を指定し取得したもの又は計画的付与により取得したものにかかわらず、実際に労働者が年次有給休暇を取得した日数(半日単位で取得した回数及び時間単位で取得した時間数を含む。)を記載する必要がある。 また、労働者名簿、賃金台帳と同様の要件を満たした上で、電子機器を用いて磁気ディスク、磁気テープ、光ディスク等により調整することは差し支えない。 |
| <就業規則への記載> | |
| 問14 | 法第39条第7項の規定による時季指定について、就業規則に記載する必要はあるか。 |
| 答14 | 休暇に関する事項は就業規則の絶対的必要記載事項であるため、使用者が法第39条第7項による時季指定を実施する場合は、時季指定の対象となる労働者の範囲及び時季指定の方法等について、就業規則に記載する必要がある。 |
第4 労働条件の明示の方法(則第5条第4項関係)
| <労働者が希望した場合> |
則第5条第4項の「労働者が(中略)希望した場合」とは、労働者が使用者に対し、口頭で希望する旨を伝達した場合を含むと解されるが、法第15条の規定による労働条件の明示の趣旨は、労働条件が不明確なことによる紛争を未然に防止することであることに鑑みると、紛争の未然防止の観点からは、労使双方において、労働者が希望したか否かについて個別に、かつ、明示的に確認することが望ましい。 |
| <「電子メール等」の具体的内容> |
「電子メール」とは、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成14年法律第26号)第2条第1号の電子メールと同様であり、特定の者に対し通信文その他の情報をその使用する通信端末機器(入出力装置を含む。)の影像面に表示させるようにすることにより伝達するための電気通信(有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることをいう(電気通信事業法第2条第1号)。)であって、①その全部若しくは一部においてSMTP(シンプル・メール・トランスファー・プロトコル)が用いられる通信方式を用いるもの、又は②携帯して使用する通信端末機器に、電話番号を送受信のために用いて通信文その他の情報を伝達する通信方式を用いるものをいうと解される。 ①にはパソコン・携帯電話端末によるEメールのほか、Yahoo!メールやGmailといったウェブメールサービスを利用したものが含まれ、②にはRCS(リッチ・コミュニケーション・サービス。+メッセージ(プラス・メッセージ)等、携帯電話同士で文字メッセージ等を送信できるサービスをいう。)や、SMS(ショート・メッセージ・サービス。携帯電話同士で短い文字メッセージを電話番号宛てに送信できるサービスをいう。)が含まれる。 「その受信する者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信」とは、具体的には、LINEやFacebook等のSNS(ソーシャル・ネットワーク・サービス)メッセージ機能等を利用した電気通信がこれに該当する。 なお、上記②の例えばRCSやSMSについては、PDF等の添付ファイルを送付することができないこと、送信できる文字メッセージ数に制限等があり、また、原則である書面作成が念頭に置かれていないサービスであるため、労働条件明示の手段としては例外的なものであり、原則として上記①の方法やSNSメッセージ機能等による送信の方法とすることが望ましい。労働者が開設しているブログ、ホームページ等への書き込みや、SNSの労働者のマイページにコメントを書き込む行為等、特定の個人がその入力する情報を電気通信を利用して第三者に閲覧させることに付随して、第三者が特定個人に対し情報を伝達することができる機能が提供されるものについては、「その受信する者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信」には含まれないことに留意する必要がある。 上記のサービスによっては、情報の保存期間が一定期間に限られている場合があることから、労働者が内容を確認しようと考えた際に情報の閲覧ができない可能性があるため、使用者が労働者に対して、労働者自身で出力による書面の作成等により情報を保存するように伝えることが望ましい。 |
| <電子メール等の「送信」の考え方> |
電子メール等の「送信」については、労働者が受信拒否設定をしていたり、電子メール等の着信音が鳴らない設定にしたりしているなどのために、個々の電子メール等の着信の時点で、相手方である受信者がそのことを認識し得ない状態であっても、受信履歴等から電子メール等の送信が行われたことを受信者が認識しうるのであれば、「電子メール等の送信」に該当するものと解される。 ただし、労働条件の明示を巡る紛争の未然防止の観点を踏まえると、使用者 があらかじめ労働者に対し、当該労働者の端末等が上記の設定となっていないか等を確認した上で送信することが望ましい。 |
| <記録の出力及び書面の作成> |
労働条件の明示の趣旨を鑑みると、使用者が労働者に対し確実に労働条件を明示するとともに、その明示された事項を労働者がいつでも確認することができるよう、当該労働者が保管することのできる方法により明示する必要があることから、労働者が書面の交付による明示以外の方法を望んだ場合であっても、電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。 この場合において「出力することにより書面を作成することができる」とは、当該電子メール等の本文又は当該電子メール等に添付されたファイルについて、紙による出力が可能であることを指すが、労働条件の明示を巡る紛争の未然防止及び書類管理の徹底の観点から、労働条件通知書に記入し、電子メール等に添付し送信する等、可能な限り紛争を防止しつつ、書類の管理がしやすい方法とすることが望ましい。 |
| <その他の留意事項> |
【明示しなければならない労働条件の範囲】 今回の改正省令については、労働条件の明示方法について改正を行うものであることから、明示しなければならない労働条件の範囲について変更を加えるものではない。 【電子メール等による送信の方法による明示の場合の署名等】 電子メール等による送信の方法による明示を行う場合においても、書面による交付と同様、明示する際の様式は自由であるが、紛争の未然防止の観点から、明示しなければならない事項に加え、明示を行った日付や、当該電子メール等を送信した担当者の個人名だけでなく労働条件を明示した主体である事業場や法人等の名称、使用者の氏名等を記入することが望ましい。 |
第5 過半数代表者(則第6条の2関係)
| <「必要な配慮」の内容> | |
| 問1 | 則第6条第4項の「必要な配慮」にはどのようなものが含まれるのか。 |
| 答1 | 則第6条第4項の「必要な配慮」には、例えば、過半数代表者が労働者の意見集約等を行うに当たって必要となる事務機器(イントラネットや社内メールを含む。)や事務スペースの提供を行うことが含まれるものである。 |