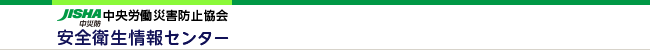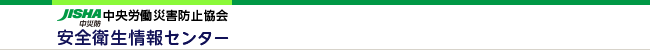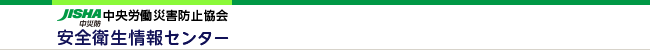
|
 |
(別添)
「職場における腰痛予防対策指針及びその解説−抜粋−」
職場における腰痛予防対策指針
1 はじめに
職場における腰痛は、特定の業種のみならず多くの業種及び作業において見られる。
これらの腰痛の発生の要因には、[1]腰部に動的あるいは静的に過度に負担を加える動作要因、[2]腰
部への振動、寒冷、床・階段での転倒等で見られる環境要因、[3]年齢、性、体格、筋力等の違い、椎
間板ヘルニア、骨粗しょう症等の既往症又は基礎疾患の有無及び精神的な緊張度等の個人的要因があり、
これら要因が重なり合って発生する。
職場における腰痛を予防するためには、作業管理、作業環境管理、健康管理及び労働衛生教育を適切
に行うことによって腰痛の発生の要因の排除又は軽減に努めるとともに、労働者の健康の保持増進対策
を進めることが必要であることから、本指針は、これらの事項について具体的に示すものである。
各事業場においては、本指針に掲げられた腰痛の基本的な予防対策を踏まえ、各事業場の作業の実態
に即した対策を講ずる必要がある。
なお、本指針では、腰痛の発生を減少させるため、一般的な腰痛の予防対策を示した上で、腰痛の発
生が比較的多い次の5作業についての作業態様別の基本的な対策を別紙により示した。
(1) 重量物取扱い作業
(2) 重症心身障害児施設等における介護作業
(3) 腰部に過度の負担のかかる立ち作業
(4) 腰部に過度の負担のかかる腰掛け作業・座作業
(5) 長時間の車両運転等の作業
2 作業管理
(1) 自動化、省力化
腰部に著しい負担のかかる作業を行わせる場合には、作業の全部又は一部を自動化又は機械化し、
労働者の負担を軽減することが望ましいが、それが困難な場合には、適切な補助機器等を導入すること。
(2) 作業姿勢、動作
労働者に対し、次の事項に留意させること。
イ 腰部に負担のかかる中腰、ひねり、前屈、後屈ねん転等の不自然な姿勢をなるべく取らないよう
にすること。このため、正面を向いて作業が行えるよう作業台等の高さ、労働者と作業台等との対
面角度の調節等を行うこと。また、不自然な姿勢を取らざるを得ない場合には、適宜、身体を保持
する台等を使用すること。
ロ 立位、椅座位等において、同一姿勢を長時間取らないようにすること。
ハ 腰部に負担のかかる動作を行うに当たっては、姿勢を整え、かつ、急激な動作を避けること。
ニ 持ち上げる、引く、押す等の動作は、膝を軽く曲げ、呼吸を整え、下腹部に力を入れながら行う
こと。
ホ 勁部又は腰部の不意なひねりを可能な限り避け、動作時には、視線も動作に合わせて移動させる
こと。
(3) 作業標準等
イ 作業標準の策定
腰部に過度の負担のかかる作業については、腰痛の予防のため、次の事項に留意して作業標準を
策定すること。また、新しい機器、設備等を導入した場合には、その都度、作業標準を見直すこと。
(イ) 作業時間、作業量、作業方法、使用機器等を示すこと。なお、作業時間、作業量等の設定に際
しては、作業内容、取り扱う重量、自動化等の状況、補助機器の有無、作業に従事する労働者の
数、性別、体力、年齢、経験等に配慮すること。
(ロ) 不自然な姿勢を要する作業や反復作業等を行う場合には、他の作業と組み合わせる等により当
該作業ができるだけ連続しないようにすること。また、作業時間中にも適宜、小休止・休息が取
れるようにすることが望ましい。
ロ その他
(イ) コンベヤー作業等作業速度が機械的に設定されている作業を行わせる場合には、労働者の身体
的な特性と体力差を考慮して、適正な作業速度にすること。
(ロ) 夜勤、交替制勤務及び不規則勤務にあっては、作業量が昼間時における同一作業の作業量を下
回るよう配慮すること。
(4) 休憩
イ 腰部に著しい負担のかかる作業を行わせる場合には、横になって安静を保てるよう十分な広さを
有する休憩設備を設けるよう努めること。
ロ 休憩設備の室内温度を、筋緊張が緩和できるよう調節することが望ましい。
(5) その他
イ 腰部に著しい負担のかかる作業を行わせる場合には、腹帯等適切な補装具の使用も慮すること。
ロ 作業時の靴は、足に適合したものを使用させること。腰部に著しい負担のかかる作業を行う場合
には、ハイヒールやサンダルを使用させないこと。
3 作業環境管理
(1) 温度
屋内作業場において作業を行わせる場合には、作業場内の温度を適切に保つこと。また、低温環境
下において作業を行わせる場合には、保温のための衣服を着用させるとともに、適宜、暖が取れるよ
う暖房設備を設けることが望ましい。
(2) 照明
作業場所、通路、階段、機械類等の形状が明瞭にわかるように適切な照度を保つこと。
(3) 作業床面
作業床面はできるだけ凹凸がなく、防滑性、弾力性、耐衝撃性及び耐へこみ性に優れたものとする
ことが望ましい。
(4) 作業空間
動作に支障がないよう十分な広さを有する作業空間を確保すること。
(5) 設備の配置等
作業を行う設備、作業台等については、作業に伴う動作、作業姿勢等を考慮して、形状、寸法、配
置等に人間工学的な配慮をすること。
4 健康管理
(1) 健康診断
重量物取扱い作業、介護作業等腰部に著しい負担のかかる作業に常時従事する労働者に対しては、
当該作業に配置する際(再配置する場合を含む。以下同じ。)及びその後6月以内ごとに1回、定期に、
次のとおり医師による腰痛の健康診断を実施すること。
イ 配置前の健康診断
配置前の労働者の健康状態を把握し、その後の健康管理の基礎資料とするため、配置前の健康診
断の項目は、次のとおりとすること。
(イ) 既往歴(腰痛に関する病歴及びその経過)及び業務歴の調査
(ロ) 自覚症状(腰痛、下肢痛、下肢筋力減退、知覚障害等)の有無の検査
(ハ) 脊柱の検査:姿勢異常、脊柱の変形、脊柱の可動性及び疼痛、腰背筋の緊張及び圧痛、脊椎棘
突起の圧痛等の検査
(ニ) 神経学的検査:神経伸展試験、深部腱反射、知覚検査、筋萎縮等の検査
(ホ) 脊柱機能検査:クラウス・ウェーバーテスト又はその変法(腹筋力、背筋力等の機能のテスト)
(ヘ) 腰椎のX線検査:原則として立位で、2方向撮影(医師が必要と認める者について行うこと。)
ロ 定期健康診断
(イ) 定期に行う腰痛の健康診断の項目は、次のとおりとすること。
a 既往歴(腰痛に関する病歴及びその経過)及び業務歴の調査
b 自覚症状(腰痛、下肢痛、下肢筋力減退、知覚障害等)の有無の検査
(ロ) (イ)の健康診断の結果、医師が必要と認める者については、次の項目についての健康診断を追
加して行うこと。この場合、(イ)の健康診断に引き続いて実施することが望ましい。
a 脊柱の検査:姿勢異常、脊柱の変形、脊柱の可動性及び疼痛、腰背筋の緊張及び圧痛、脊椎
棘突起の圧痛等の検査
b 神経学的検査:神経伸展試験、深部腱反射、知覚検査、徒手筋力テスト、筋萎縮等の検査
(必要に応じ、心因性要素に関わる検査を加えること。)
c 腰椎のX線検査(医師が必要と認める者について行うこと。)
d 運動機能テスト(医師が必要と認める者について行うこと。)
ハ 事後措置
腰痛の健康診断の結果、労働者の健康を保持するため必要があると認めるときは、作業方法等の
改善、作業時間の短縮等必要な措置を講ずること。
(2) 作業前体操、腰痛予防体操
イ 作業前体操の実施
腰痛の予防を含めた健康確保の観点から、次のとおり作業前体操を実施すること。
(イ) 始業時に準備体操として行うこと。
(ロ) 就業中に新たに腰部に過度の負担のかかる作業を行う場合には、当該作業開始前に下肢関節の
屈伸等を中心に行うこと。
なお、作業終了時においても、必要に応じ、緊張した筋肉をほぐし、血行を良くするための整
理体操として行うこと。
ロ 腰痛予防体操の実施
重量物取扱い作業、介護作業等腰部に著しい負担のかかる作業に常時従事する労働者に対し、適
宜、腰痛予防を目的とした腰痛予防体操を実施すること。
腰痛予防体操には、[1]関節可動体操、[2]軟部組織伸展体操、[3]筋再建体操の3種があり、実施
に当たっては、その目的に合ったものを選択すること。
5 労働衛生教育等
(1) 労働衛生教育
重量物取扱い作業、介護作業等腰部に著しい負担のかかる作業に常時従事する労働者については、
当該作業に配置する際及び必要に応じ、腰痛の予防のための労働衛生教育を実施すること。
当該教育の項目は次のとおりとし、その内容は受講者の経験、知識等を踏まえ、それぞれのレベル
に合わせて行うこと。
[1] 腰痛に関する知識
[2] 作業環境、作業方法等の改善
[3] 補装具の使用方法
[4] 作業前体操、腰痛予防体操
なお、当該教育の講師としては、腰痛の予防について十分な知識と経験を有する者が適当である
こと。
(2) その他
腰痛を予防するためには、職場内における対策を進めるのみならず、労働者の日常生活における健
康の保持増進が欠かせない。このため、産業医等の指導の下に、労働者の体力や健康状態を把握した
上で、バランスのとれた食事、睡眠に対する配慮等の指導を行うことが望ましい。