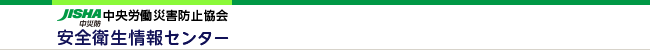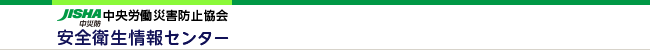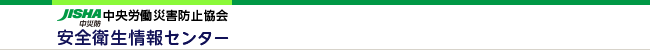
|
 |
別紙 作業態様別の対策
I 重量物取扱い作業
重量物を取り扱う作業を行わせる場合には、単に重量制限のみを守るのではなく、取扱い回数等作業
密度を考慮し、適切な作業時間、人員の配置等に留意しつつ、次の対策を講ずること。
(1) 自動化、省力化
イ 重量物取扱い作業については、適切な自動装置、台車の使用等により人力の負担を軽減すること
を原則とすること。なお、作業の自動化が困難な場合は、適切な装置、器具等を使用して、できる
だけ人力の負担を軽減すること。
ロ 人力による重量物取扱い作業が残る場合には、作業速度、取扱い物の重量の調整等により、腰部
に過度の負担がかからないようにすること。
(2) 重量物の取扱い重量
イ 満18歳以上の男子労働者が人力のみにより取り扱う重量は、55kg以下にすること。
また、当該男子労働者が、常時、人力のみにより取り扱う場合の重量は、当該労働者の体重のお
おむね40%以下となるように努めること。
ロ (1)の重量を超える重量物を取り扱わせる場合には、2人以上で行わせるように努め、この場合、
各々の労働者に重量が均一にかかるようにすること。
(3) 荷姿の改善、重量の明示等
イ 荷物は、かさばらないようにし、かつ、適切な材料で包装し、できるだけ確実に把握することの
できる手段を講じて、取扱いを容易にすること。
ロ できるだけ取り扱う物の重量を明示すること。
ハ 著しく重心の偏っている荷物については、その旨を明示すること。
ニ 手カギ、吸盤等補助具の活用を図り、持ちやすくすること。
(4) 作業姿勢、動作
労働者に対し、次の事項に留意させること。重量物を取り扱うときは急激な身体の移動をなくし、
かつ、身体の重心の移動を少なくする等できるだけ腰部に負担をかけない姿勢で行うことを原則とす
ること。
このため次の事項に留意すること。
イ できるだけ身体を対象物に近づけ、重心を低くするような姿勢を取ること。
ロ はい付け又ははいくずし作業においては、できるだけはいを肩より上で取り扱わないこと。
ハ 床面等から荷物を持ち上げる場合には、片足を少し前に出し、膝を曲げ、腰を十分に降ろして当
該荷物をかかえ、膝を伸ばすことによって立ち上がるようにすること。
ニ 腰をかがめて行う作業を排除するため、適切な高さの作業台等を利用すること。
ホ 荷物を持ち上げるときは呼吸を整え、腹圧を加えて行うこと。
ヘ 荷物を持った場合には、背を伸ばした状態で腰部のひねりが少なくなるようにすること。
(5) 取扱い時間
イ 取り扱う物の重量、取り扱う頻度、運搬距離、運搬速度等作業の実態に応じ、小休止・休息をと
る、他の軽作業と組み合わせる等により、重量物取扱い時間を軽減すること。
ロ 単位時間内における取扱い量を、労働者に過度の負担とならないよう適切に定めること。
(6) その他
腹圧を上げるため、必要に応じ、腰部保護ベルト、腹帯等を使用させること。
II 重症心身障害児施設等における介護作業
重症心身障害児施設等で、入所児、入所者等(以下「入所児等」という。)の介護を行わせる場合に
は、姿勢の固定、中腰で行う作業や重心移動等の繰り返し、重量の負荷等により、労働者に対して腰部
に静的又は動的に過重な負担が持続的に、又は反復して加わることがあり、これが腰痛の大きな要因と
なる。このため、次の措置を講ずることにより、作業負担の軽減を図ること。
なお、肢体不自由児施設、特別養護老人ホーム等における介護に係る腰痛の予防についても、次の措
置に準じ、実情に応じた対策を講ずるよう努めること。
(1) 作業姿勢、動作
中腰で行う作業や腰をひねった姿勢を長く保つ作業等を行わせる場合には、適宜小休止・休息をと
る、他の作業と組み合わせる等により、同一姿勢を長時間続けないようにさせること。
イ 介護の方法
介護のために入所児等を床面又はベッドからかかえた状態で作業を行わせるときの作業姿勢は
Iによること。また、体重の重い入所児等の体位の変換、移動等は、複数の者で行わせること。
ロ 食事介助の方法
食事の介助を行う者に対しては、ベッドに横座りすることを避け、椅子に座って入所児等に正面
を向くか、ベッド上でいわゆる膝まくらの姿勢を取らせること。ただし、同一の姿勢を長く続けさ
せないこと。
(2) 作業標準
使用機器、作業方法等に応じた作業標準を策定すること。また、作業標準には、入所児等の身体等
の状態別、作業の種類別の作業手順、役割分担、作業場所等についても明記すること。
(3) 介護者の適正配置
介護者の数は、施設の構造、勤務体制、療育内容及び入所児等の心身の状況に応じた適正なものと
するよう努めること。
なお、やむを得ない理由で、一時的に繁忙な事態が生じた場合は、介護者の配置を随時変更する等
により、腰部負担の大きい業務が特定の介護者に集中しないように十分配慮すること。
(4) 施設及び設備の構造等の改善
不適切な施設及び設備は、作業姿勢に密接に関係するので、適切な介護設備、機器等の導入を図る
とともに、介護に関連した業務を行うために必要な施設、機器等についても適切なものを整備するこ
と。
また、作業姿勢を適正化するため、実際の作業状況を検討し、次の改善を図ること。
イ 室の構造等
入所児等の移送は、できるだけストレッチャーによって行うようにし、通路及び各部屋にはスト
レッチャーの移動の障害となるような段差等を設けないこと。
ロ 浴槽の構造等
(イ) 浴槽、洗身台、シャワー設備等の配置は、介護者の無用の移動をできるだけ少なくするような
ものとすること。
(ロ) 浴槽の縁、洗身台及びシャワーの高さ等は、介護者の身長に適合するものとすること。なお、
これらの高さが適切でないこととなる介護者に対しては、滑りにくい踏み板等を使用させること
も考慮すること。
(ハ) 移動式洗身台、ローラコンベヤー付き洗身台、移動浴槽、リフト等の介助機器の導入を図ること。
ハ ベッドの構造等
ベッドの高さは、入所児等の身体状況等も考慮し、介護者の身長に適合するものとすること。
なお、これらの高さが適切でないこととなる介護者に対しては、履物、踏み板等を使用させるこ
とも考慮すること。
ニ 付帯設備等
介護中に利用できる背もたれのある椅子や堅めのソファー等を適宜配置し、くつろいで座れるよ
うにすること。また、介護に必要な用具等は、出し入れしやすい場所に収納すること。
ホ 休憩
休憩設備は、労働者の数及び勤務体制を考慮し、利用に便利で、かつ、くつろげるものとするこ
とが望ましい。
(5) その他
腹圧を上げるため、必要に応じ、腰部保護ベルト、腹帯等を使用させること。
III 腰部に過度の負担のかかる立ち作業 (略)
IV 腰部に過度の負担のかかる腰掛け作業・座作業 (略)
V 長時間の車両運転等の作業 (略)
「別紙 作業態様別の対策」について